脊柱管狭窄症の考察と改善方法
脊柱管狭窄症の考察
脊柱管狭窄症とは、簡単に言いますと、背骨の中の脊髄が通っている管が何らかの原因で狭くなる、狭窄する事を言います。
狭窄する原因としては、腰椎椎間板ヘルニアや椎骨の変形、すべり症、腫瘍、骨棘など脊柱の通り道を阻害するものが考えられます。
先天的に脊柱管狭いなど、脊柱管が狭窄していても特に症状が出ない方もおられます。
しかしながら、上記の原因となるものが、神経を圧迫してしまうと下肢に痺れ、脱力感、歩行障害などを感じ、生活に大きな支障が生じますので治療が必要になります。
一番典型的な症状は、歩行中に痛みにより歩けなくなり、少ししゃがんでじっとしていると、改善されまた歩行が可能になるという状態です。
なぜこのような状態が生じるかと説明しますと、通常歩行中は腰部が少なからず伸展する状態になりますが、その伸展方向への圧力が脊柱管を狭くするので、神経の圧迫が増強され痺れの増悪を生じます。
そして、しゃがむという行為は、腰部を屈曲する方向へのベクトルが生じ、脊柱管を拡げる事になりますので、神経の圧迫が軽減し症状の緩和が図れることになります。
この腰部の屈曲でも症状が緩和しない方は、大腿動脈の動脈硬化による酸素供給不足による筋肉の疼痛症状、閉塞性動脈硬化症である可能性があります。
初回で脊柱管狭窄症などの場合、医療機関を選択する時に、一番最初にカイロプラクティックを選ばれる方は少ないと思われますが、仮に治療を続けても改善が無い場合は、腫瘍などの原因も考えられますので、医療機関に照会し、MRIなどの検査をして頂かなければなりませんので、鑑別診断を考えながら、治療を進めて行きます。
閉塞性動脈硬化症に関しては、大腿動脈のルートの脈診で見極める事が出来ます。
脊柱管狭窄症は基本的には坐骨神経痛の症状が呈されます。
しかしながら全てが神経性の原因ではなく、お尻や脚の筋肉などの筋性のトリガーポイントとが原因のものもございます。まず何が原因となるものが何かを鑑別していく事が改善への近道となります。中々整形外科などの電気療法や牽引療法で改善するのは難しいのではないでしょうか。
それでは、更に脊柱管狭窄症の考察を進めて行きましょう。
脊柱管狭窄症の主な原因
- 腰椎椎間板ヘルニアによる圧迫によるもの
- すべり症や骨の変形などによるもの
- 臀部にある深部筋の梨状筋などによる圧迫によるもの
- 脚の裏側のハムストリングや坐骨神経ラインでの筋圧迫によるもの
- 大腿動脈の動脈硬化
- ハイヒールや妊娠による過度な前弯
- 自律神経性のもの
- 加齢による痛みを抑制するメカニズムの衰えによるもの
- 事故などによる外傷によるもの
- 過度のトレーニングによる過伸展によるもの
脊柱管狭窄症が及ぼす身体症状
- 下枝への痺れ・痛み
- 歩行不全
- 臀部痛
- 身体の可動域制限
- 不眠
- 不安症・うつ病
- 長時間立てない
- 身体を真っすぐ保てない
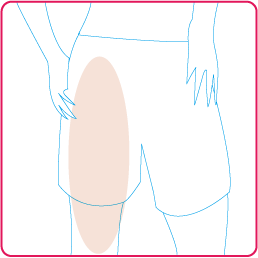
脊柱管狭窄症に関与する主要組織
関節組織
- 腰椎椎間板
- 仙腸関節
- 股関節
- 膝関節
- 足関節
筋肉組織と神経組織
- 坐骨神経(L4~S3神経の集合体)
- 総腓骨神経の枝(L4~S2神経の集合体)
- 脛骨神経の枝(L4~S3神経の集合体)
- 最長筋(脊髄神経後枝の外側枝C1~L5)
- 大殿筋(下殿神経L4~S2) 作用・股関節の伸展と外旋
- 中殿筋(上殿神経L4~S1) 作用・股関節の外転
- ハムストリング(脛骨神経等L4~S2) 作用・股関節の伸展、膝関節の屈曲
- 腰方形筋(腰神経叢の枝L12~L3) 作用・腰部の側屈
- 腹筋群(胸神経T5~T12) 作用・体幹の屈曲、回旋、側屈、腹圧上昇
- 梨状筋(仙骨神経叢L5~S2) 作用・股関節外旋
上記のように脊柱管狭窄症は、多くの組織が関わって生じる疾患です。脊柱管狭窄症がある場合や診断を受けた場合でも、坐骨神経痛には坐骨神経から下腿で分派される総腓骨神経と脛骨神経も含まれ、下腿の痺れや足部の痺れなどは、これらの神経のラインでの圧迫によるものが多いです。長腓骨筋や踵の内側での圧迫で症状が診られることもあります。このような場合は、腓骨や踵骨の調整で改善される事が多いです。
ですので、臨床としては、あまり腰椎椎間板ヘルニアや脊柱管狭窄症が原因と思われる坐骨神経痛は少なく、坐骨神経の走行ラインでの障害によって痺れや痛みが多いです。
つまり、脊柱管狭窄症と診断されても、それが原因で無いことが多いという事です。
脊柱管狭窄症に対する改善治療
問診の重要性
鑑別診断の重要性

閉塞性動脈硬化症が疑われる場合の足背動脈の脈診です。
ここで脈拍が感じられない場合は、動脈硬化症などで血液循環不全がある事が推察されますので、腰部の治療などでは、改善しない可能性が高いです。
大腿動脈の新生血管を作る必要がありますので、新生血管を作る為、また違うアプローチを行います。

神経に伸張の刺激を入れ、痛み痺れの有無を確認します。
脊柱管狭窄症による症状が緩和するか確認致します。
屈曲による緩和作用が起きるのか等の検査です。

伸展回旋の刺激を入れることで、症状にどのような変化があるのか調べています。
基本脊柱管狭窄症は空間が拡大する屈曲で緩和し、狭小する伸展刺激で痛みが出ることが多いです。回旋屈曲など分節で細かく検査することで、どの分節のどの動きで症状が緩和するか確かめて行きます。

検査で、脊柱の狭窄が原因で神経症状が出ていることが確認出来れば、腰部の牽引を入れながら空間を拡げることで、除圧の状態を維持出来るように施術していきます。これで症状の緩和を確認出来れば、更に治療を進めて行きます。
坐骨神経痛や痺れの臨床報告は坐骨神経痛の改善治療日記をご覧ください。
・腸腰筋過緊張による脊柱管狭窄症悪化の改善治療日記
・尻もちによって生じた脊柱管狭窄症の改善治療日記
・ある特定の姿勢によって生じた両脚のしびれの改善治療日記
・腰椎分離症に起因する腰痛の改善治療日記
・腰椎すべり症に起因する鼠径部から内ももの痛みの改善治療日記
脊柱管狭窄症の症状でお寄せ頂いた声




